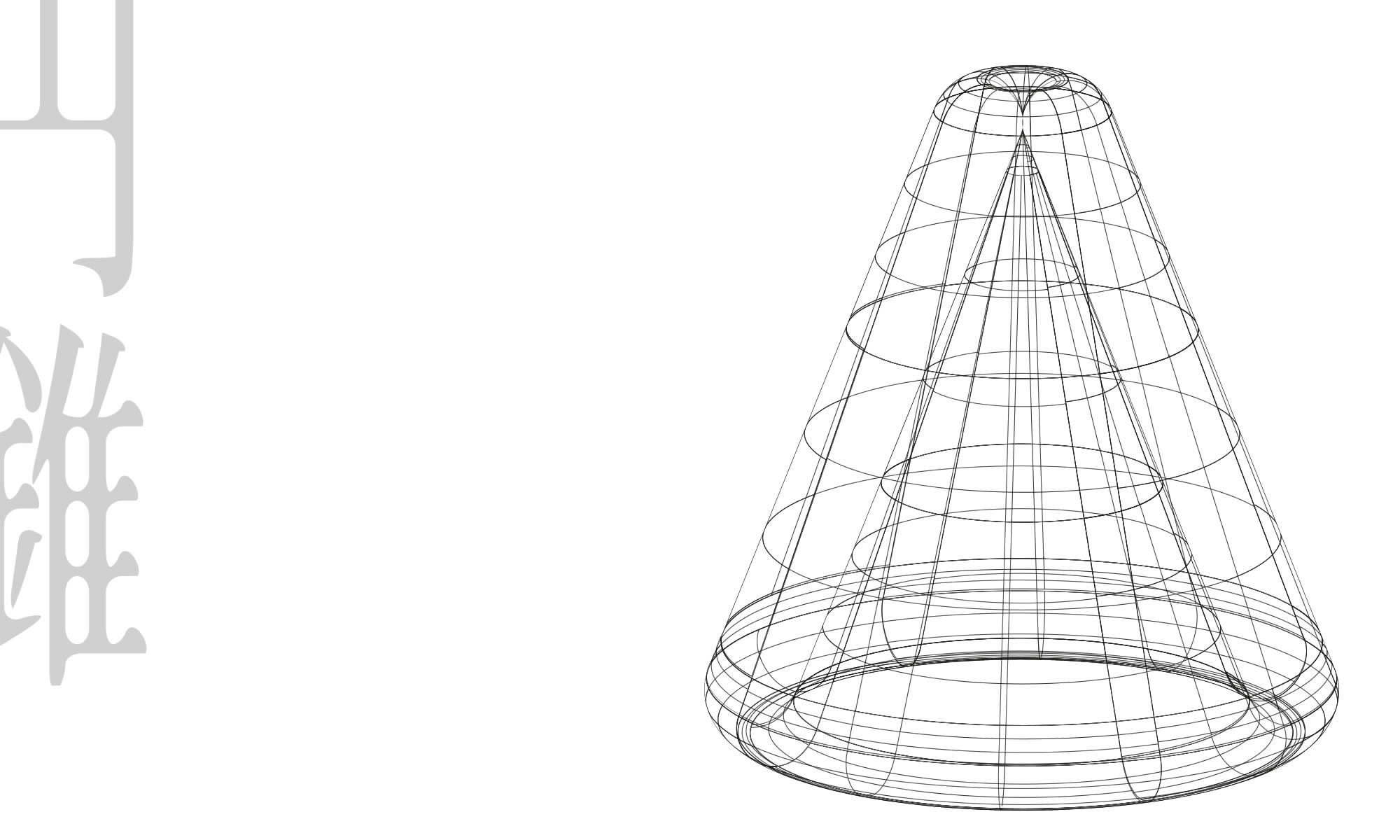選評 第8回円錐新鋭作品賞
何一つ明かりの無い暗黒の中で生きていくことができないように、人間として生き、生活するにあたっては、生き方の型が必要である。その型を文化とか文明とか常識と呼ぶ。そうした型のうち最大のものは言葉である。生活の中で他人と意思疎通をする上で言葉は無くてはならない。しかし、それが型であるということは、既成の形に当て嵌めるということだから、各自の内面の微妙さをうまく表せないことも多い。俳句も一つの型である。時代によって型としてのあり方を変えつつ、その型を使うことによって、人は形にならないモヤモヤ混沌としたものに形を与え、そこに喜びを感じてきた。その型の最たるものが五七五の定型であり、季語を使うという約束である(と思われている)。しかし、それが型である限り、そこから生まれるものは既成の表現のくり返しとなり、新鮮さを失う。型のあり方に挑み、真に生き生きした美しさを掴もうとする作品を高く評価した。
第一位は織田亮太郎「■■者」。
■■派反■■派皆裸
痩身の■■省を出て四日
脳髄を■■色に滴りぬ
「■■」は、検閲されたあとの伏せ字のようであり、また、活字印刷における「げた記号(〓)」のようでもある。先年の本賞投稿作品にも、こうした試みはあったので、初めて行われたものではない。だが、一般的に、やはりこれは斬新な試みであることは間違いない。かつ、単に斬新であるだけではなくて、伏せ字の如き記号を導入することにより、作品に戦時下や占領下のような時代感、即ち不穏にして危険な印象を生んでいる。一般に俳句に対して抱かれるところの穏やかな趣味性だとか、安らげる文芸だとかいった印象に対して真っ向から異を唱えている。この挑戦の姿勢が良い。とはいえ、全く読者を突き放しているかというと、そうではない。「■■」の部分、音読できないように見えるが、よく見ると、「■」の一つが二音分であるとわかる。「■■」は例えば「バツバツ」と読める。するといわゆる五七五の型に収まるのだ。かつ、この二十句は全て季語をもつ。「四日」を一月四日、「滴り」を夏山の岩壁からの水滴、と捉えた場合に季語となる。かつ、全体が春夏秋冬の順に並ぶ。ただし、本作での季語の使われようを見ると、いわゆる歳時記的な用法ではない。こうしたことはどういうことなのか? ■■を使うという前衛性を空回りさせずに作品として成立させるために、そうしたいわゆる俳句らしさによって支えとしたのであろうか。あるいは、季語や四季順列という既成の観念への批評と見ることもできる。題名は「■■祭」とすれば、それも季語への批評となる。
第二位は加藤閑「無垢と爛熟」。
夏至の日の雪法王は口で受ける
少年に舌を吸はせる獏老いて
叫喚止まず教室の天上にイコン
全体に夏石番矢風の味わいがあり、斬新さと不穏さの魅力がある。夏の空から雪が舞い落ち、それを法王が聖餐のように口で受け止める。その光景はまさに番矢風の見事な絵である。老いた獏が少年の舌を吸う図はあたかも山本タカトか丸尾末広を思わせる。「叫喚」は教室の子供たちと結び付くことで存在感を生んでいる。その天上(天井ではない)に、ロシア正教風のイコンが幻視される。
第三位はミテイナリコ「Like 唖 排句 Gocco(ご挨拶ver1.0)」
詩に焚くない殻遺棄て煎る生盆
その話一反木綿豆腐濾す
深夜二時見えない虹の先の些事
一句目は「しにたくないからいきているいきぼん」と読む。漢字変換のミスのようだが一種の語呂合わせでもある。二句目は「一旦」という副詞と「一反木綿」との掛詞。三句目は「ニジ」「ニジ」「サジ」という音の遊び。つまり、俳諧本来の滑稽味がここにある。特に一句目は「生盆」という、内容も語の響きも奇妙な季語と巧みに響き合っている。
以下、審査用の資料に掲載された順に全ての応募作に触れていこう。
1 岡田美幸〈お雑煮の中の鳴門が微笑せり〉鳴門巻の渦巻模様が新春を寿ぐ。
2 小里今日子〈ひとつぶの葡萄のなかの海鳴りや〉深い海の色をした葡萄。
3 大野美波〈あの子さえいなかったなら木下闇〉小学生が同級生を妬む…。恋人を奪われた若い女の思い…。重荷となる子どもを持った親の心境…。誰しも抱いたことがある、心の中の闇を形象化。
4 赤木真理〈鞠かがる臍の緒二つ芯として〉出産時に亡くなった赤子の臍の緒。それを鞠とすることで、その子にも遊んで欲しい、という思い、なのか。
5 尾内甲太郎
〈錆びついた
ロケット
枯野は
剛毛〉
不要のロケットが枯野に廃棄されたか。
6 垣内孝雄〈鳰の湖なまづたくさんをりますよ〉琵琶湖に永田耕衣がいる趣。
8 坂西涼太〈十二月八日コップに水ふるへ〉戦闘機通過の振動か。繊細な感性。
9 山田すずめ〈町にまた増える戒名冬の虫〉個々の霊は時を経て先祖の霊と一体化するが、文字としての戒名は残り、増え続ける。その存在を冬の虫と重ねるのは辛辣な批評性がある。
10 播磨陽子〈うかうかと狐火の尾か腹か踏む〉百鬼夜行図の中、狐火の後ろにいるうっかり者の物の怪か。落語の趣も。
11 紅紫あやめ〈祝日も忌日も蜜柑揉んでいる〉なすことの無き人の単調な毎日を具象化。ある種の永遠性がある。
13 植田井草〈さよならは渋民駅の次の駅〉渋民は石川啄木の故郷。石川啄木の人生の場面か。静かなロマン。
14 五月ふみ〈外套に臓器と臓器隔てられ〉人間とは即ち臓器であり、その囲いとして外套がある、という鋭い幻視。
15 正山オグサ〈ミサイルに小さき羽や雪催ひ〉恐ろしい兵器が小鳥の様に見える。暴力と可憐さとの一体化。
16 村瀬ふみや〈鶏頭花無声映画に火の匂ひ〉鶏頭の映像に炎を感じる鋭い目と鼻。鶏頭は無言のまま燃えている。
17 千住祈理〈生きたさの自自自自荷重冬の海〉生の衝動が重荷となる詩人の体感。「自我」の重さは近代人の宿命。
18 菅井香永〈初旅やあんパンの餡まで遠し〉食べることも旅だという洞察。
19 涼野海音〈次の世も次の世もまた雪女〉一つの魂が生まれ変わりつつ雪女であり続ける。雪女への優しさとロマン。
20 三島ちとせ〈墓参りスプーン曲げられる叔父と〉素敵な叔父さん。羨ましい。
21 あおい月影〈小春日や監視カメラのない戸棚〉題は「コンビニの日常」。監視カメラだらけの店内に一箇所だけ、カメラに映らない所がある。それは冬の暖かな日のようだ。共感します。
22 相田えぬ〈頭痛吐き気眩暈のち冴える〉季語「冴える」が気語となる面白さ。
23 高橋花紋〈これは純文学あれは寒鴉〉「これ」が何か気になる。作品自体か。
24 藤雪陽〈天心に集へる送り火の煙〉天の中心に天国への入口を見る深い視線。帰る霊のターミナル。
25 青木ともじ〈初夢に君はゐなかつたと思ふ〉「と思ふ」の曖昧さに現代人のあり方が投影されており、現代的である。
26 佐藤研哉〈極月の上映中の小さき地震〉非現実から現実へ戻る感覚を形象化。
27 楠本奇蹄〈冥婚の喉に白魚わだかまる〉冥婚は死者との婚礼。その参列者が白魚を食べると喉に引っ掛かる。不気味だ。そこに詩的実感がある。
28 有瀬こうこ〈寒鯉の口がUFO呼んでゐる〉鯉の口という凡庸な素材を、誰も詠んだことのない非凡な観点で描く。
29 貴田雄介〈平和とは空しき言葉冬荒野〉平和は人類にとって最重要概念だが、現実にかくも裏切られている言葉は無い。その歎きを「冬荒野」が象徴。
30 山本たくみ〈ばいきんをなすりつけあふさくらかな〉小学校での日常を教員の視点からシニカルに描いた連作。面白い句が沢山あり、特に掲句は学校を越えた社会批評として普遍性がある。
31 佐々木歩〈腫瘍から焚火の音がしてをりぬ〉ザ・バンドの『南十字星』の如く焚火にはロマンティックな趣きがあるが、掲句はそれを踏まえつつ巧みに異化している。三鬼の「水枕」に迫る。
32 平良嘉列乙〈領土・領海・領空、炬燵に伸ばす足〉炬燵での陣地争いという卑近なことと国際政治との落差が俳諧。
33 平野光音座〈熱に倦みアセチルサリチル酸残響〉アスピリンが響く感覚を活写。
34 本多遊子〈春宵一刻キープのボトル拭くをとこ〉滑稽な様子を切り取る観察眼。拭く姿の可笑しさを巧みに書く。
35 かくた〈北窓の網戸が破けていた〉自由律のような味わい。破けていたってええじゃないか、という気持ちになれます。俳諧性があります。
36 古田秀〈地下鉄は都市の腸クリスマス〉人間は都市に吸収される食物に過ぎない。都市こそが主人だと明察している。
37 髙田祥聖〈報はれぬ案山子ばかりやおなか空く〉風雨に晒されて働いても感謝されない案山子達への切ない共感。
39 杢いう子〈膵臓脾臓とささやき交わす菊花展〉内臓同士が身体の主の事を相談。菊の香りに誘われて。
40 ばんかおり〈喉奥の目薬あまき銀河かな〉目薬が溢れて口に入る。飛躍が絶妙。
41 川田果樹〈凍る水面にいまかいまかと触れてゐた〉今凍りつつある水面の感触。風狂の精神。
42 七瀬ゆきこ〈バーバーのーのひとつが暖かし〉「ー」は「アー」と読むのか。小沢昭一の俳句のような飄逸な味わい。
43 藤白真語〈とりあえずパンツを履いてからビール〉一人暮しでも、履いてから。秀逸な現代川柳の趣。
44 立木司〈風船が押すな押すなと死出の山〉冥府を描く。独特の感性が秀逸。
45 花島照子〈早起きの九月の真水飲み干して〉「真水」がおいしそうで印象深い。
46 クズウジュンイチ〈うつぶせのうしろあたまのほととぎす〉呪文のような不思議な味わい。平仮名表記も成功。
47 木佐優士〈秋日傘母が仏花をぶつた切る〉仏花は供花か。それを傘で切る凄さ!
48 とみた環〈寒烏・折り重なりて祈りけり〉中黒の生むリズム感が快い。
49 横田縞〈耳の奥に戦ぐ花野はいつも雨〉目や胸の奥ではなく、耳の奥。簫簫たる雨の音の花野という美しい内面世界。「戦ぐ」の効果で古戦場を想起。
50 海音寺ジョー〈端材で作れとの下知オリオン座〉工場の景だが、神話のようだ。ギリシャ神話の裏話?
51 里山子〈祈りいま枯野があくびしたような〉真面目に祈っている時に情況に茶化される。かえって祈りの真摯さが滲む。宮澤賢治の童話のようだ。
52 沼野大統領〈草相撲敗けて螢のにほひかな〉土俵も無い文字通りの草相撲。地面に転がされると、そこに螢が舞った。
53 白夜マリ〈春暁の喉の奥から群青犬〉ダリの絵のようなシュルレアリスム。
54 奈良香里〈途中まで折り鶴だつた夏の雲〉鶴を折っていたら、真夏の大きな雲になってしまった。キノコ雲を思わせる。口語「だった」が効果的だ。
55 三浦にゃじろう〈どんぐりを拾って変わる未来かな〉個人の人生にもバタフライエフェクトがある。希望を示している。わらしべ長者の現代版?
56 菊池洋勝〈せめて足だけでもお湯に浸けますか〉少しでもリラックス。少しでもゆとりを。俳句の存在理由を示す句。
57 小夏すず子〈苺ジャム昨夜の傷と同じ色〉苺ジャムと傷口とを重ねる鋭敏さ。
58 三枝ぐ
〈肉の虚
アンモナイトか
泡雪か〉
掲句以外にも印象的な多行句あり。
59 駒野繭〈春休みポストに挨拶してまわる〉郵便箱のことだろう。チャップリン演じる放浪紳士の如き、世界への接し方。作者の心優しさが滲む。
60 日月連〈花園に分け入つてあるタイヤ痕〉可憐な秋の草花を自動車が蹂躙!世界を脅かすものへの作者の悲しみ。
61 加藤幸龍〈春の夜の人魚きゆうきゆう産卵す〉擬態語が面白い。見たことのないものを見せてくれる面白さである。
62 石川聡〈名画座に来しが廃業春北斗〉寂しい気持がよく出ている。
63 石川順一〈十二月二掛ける二掛ける三掛ける〉語呂がよいので覚えやすい。
64 内野義悠〈起き抜けの水ふくろふと分け合はむ〉フクロウとの交歓に好感。
65 詠頃〈小鳥来るベッドを這っている手首〉気色悪さが気持ちいい!
66 田中目八〈おおかみの中でねずっと恋しよう〉狼の胃の中か? 斬新だ。
67 あさふろ〈蘖ゆるクローゼットのラヂオかな〉ラジオから芽が出る。凄い。
68 郡司和斗〈獅子舞の中の父より鍵もらふ〉獅子舞と鍵との組み合わせが秀逸。中本昌人の〈なまはげの指の結婚指輪かな〉と並べたくなる秀作。
69 紺之ひつじ〈己が雪にまへがみ濡るる雪をんな〉前髪の具体性が上手い。
70 細村星一郎〈マグマただ滾る 扇を落としても〉扇は和歌以来、無数に詠まれるが、マグマに落とすのは空前の壮挙。
71 岡一夏〈便器みな正しき水位花八手〉映画『パーフェクトデイズ』の主人公が俳句を作ったらこうなるだろうか。
72 兎森へる〈虎落笛ネリエニヌルル家兎ノクチ〉兎用の練り餌があるとは知らないが、不気味な感じが凄い。
お疲れ様でした。珈琲でも飲みましょうか。なに? 酒のほうが良いって? あっ、澤さんでしたか!